
ついこのあいだ、「スクルージ」でおじゃました、日生劇場。前回は「ラブネバ」からの信じられないレベルでのお久しぶり感でしたが、今回は「ただいまー!」くらいの感覚です。
「バンズ・ヴィジット」は2018年トニー賞授賞式で、作品賞を含む10部門を独占した作品(11部門ノミネートされた)。
そんなに凄いんか…。と思いつつ、「いいぞーー!!!」みたいな声も聞こえてこなくて…正直観劇しようか悩んでいました。
最初は「ダディ・ロングレッグズ」みたないハートフルなものをイメージしていたのですが、実際観てみると、今までのどんなミュージカルとも違う!と感じます。
良いか、悪いかはまた別(笑)で、好みは分かれそう。一般的なミュージカルに求められる「ドキドキ☆ワクワク」や「ハッピー」「闇深っ!」といった緩急がものすごく少ないのです。
その在り方は、いい意味で「異質」。
トニー賞10部門の栄冠を理解するには、おそらく1回の観劇じゃ足りないんだろうな…と思いつつも、確実に観てよかったミュージカルでした。


フロアには、トニー賞のトロフィーも飾ってありました。すげ~!!!
- キャスト
- あらすじ
- 感想(おおきなネタバレなし)
・トゥフィーク(指揮者):風間杜夫
・ディナ:濱田めぐみ
・カーレド(トランペット):新納慎也
・イツィク:矢崎 広
・サミー:渡辺大輔
・パピ:永田崇人
・イリス:エリアンナ
・ツェルゲル:青柳塁斗
・シモン(クラリネット):中平良夫
・電話男:こがけん
・アヴラム:岸 祐二
・警備員:辰巳智秋
・ジュリア:山﨑 薫
・アナ:髙田実那
・サミーの妻:友部柚里
・カマール(バイオリン):太田惠資
・警察音楽隊(マルチリード):梅津和時
・警察音楽隊(チェロ):星 衛
・警察音楽隊(ウード):常味裕司
・警察音楽隊(ダルブッカ):立岩潤三
あらすじ
エジプトのアレクサンドリア警察音楽隊が、イスラエルの空港に到着した。彼らはペタ・ティクヴァのアラブ文化センターで演奏するようにと招かれたのだった。しかし手違いからか、いくら待っても迎えが来ない。誇り高い楽隊長のトゥフィーク(風間杜夫)は自力で目的地に行こうとするが、若い楽隊員のカーレド(新納慎也)が聞き間違えたのか案内係が聞き間違えたのか、彼らの乗ったバスは、目的地と一字違いのベト・ハティクヴァという辺境の街に到着してしまう。
一行は街の食堂を訪れるが、もうその日はバスがないという。演奏会は翌日の夕方。食堂の女主人ディナ(濱田めぐみ)は、どこよりも退屈なこの街にはホテルもないので、自分の家と常連客イツィク(矢崎広)の家、従業員パピ(永田崇人)と店に分散して泊まるよう勧める。
トゥフィークとカーレドはディナの家に案内される。部屋でくつろいだ後、トゥフィークはディナの誘いで街をみて廻ることにする。レストランに入った二人は、音楽について語り合い、少しずつ打ち解けるが、ディナと関係を持つサミー(渡辺大輔)と彼の妻(友部柚里)が現れると、ぎこちない空気になる。
トゥフィークの筆頭部下のシモン(中平良夫)とカマール(太田惠資)は、イツィクの家に招かれる。義父のアヴラム(岸祐二)は共に食卓を囲んでもてなすが、イツィクの妻イリス(エリアンナ)は、誕生日に見知らぬ人たちを連れてきた夫に不満が募る。おとなしい楽隊員を前に話は弾まないが、話題が音楽のことに向くと、ようやく場がなごんで来る。
カーレドは外に出ると、店の前で待ち合わせをしているパピに出くわす。パピは、友人ツェルゲル(青柳塁斗)とその彼女アナ(髙田実那)に紹介されて、ジュリア(山﨑薫)と四人でデートをするのだ。カーレドは嫌がるパピに頼み込んで、一緒に街に連れ出してもらう。警備員(辰巳智秋)にすごまれながらも、スケート場で遊びはじめる五人だが、女性に慣れていないパピは、ジュリアを泣かせてしまう。カーレドはパピの指南役となり、手取り足取り彼女を慰めさせる。~公式サイトより抜粋~
公衆電話の前では、彼女からの連絡をひたすら待ち続ける電話男(こがけん)が立っている。店の外では、楽隊員たち(梅津和時、星衛、常味裕司、立岩潤三)が、思い思いに音楽を奏でている。言葉も文化も異なる隣国の人間達が交わる一夜が、更けていく。
迷子になった警察音楽隊は、果たして演奏会に間に合うのだろうか?
全体の感想(大きなネタバレなし)
「さほど遠くない昔、楽隊がエジプトからやってきた あなたは、聞いたことがないだろう たいしたことではなかった」ミュージカルのはじめと、終わりを締めくくる言葉。
「たいしたことではなかった」本当にその言葉通りでした。
行き先を間違えた警察音楽隊が、何もない寂れた町にたどりついて、町の人と一夜を共にし、目的の場所へと去っていった。
ただそれだけ。それだけの話なのに、そこにある奥深さは凄かったのです。
舞台やミュージカルは、いつも【非日常】に誘ってくれるものだけど、「バンズ・ヴィジット」に関しては、すべてが【ベイト・ハティクヴァの町の人の日常】でした。
勝手なイメージだけど、こんな感じ↓
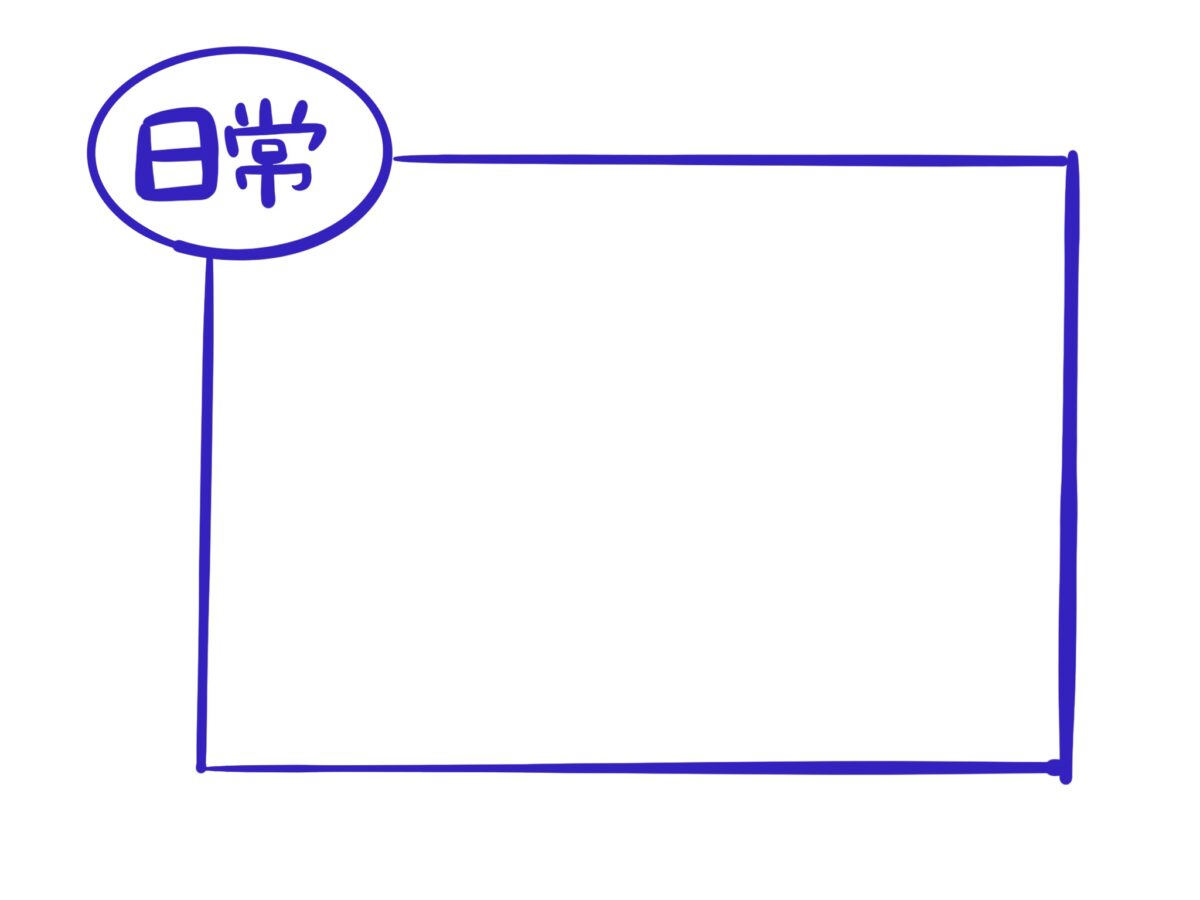
いつも見ている日常の風景。その中身を音楽が形にして拾い上げて、私たちに届けてくれる。
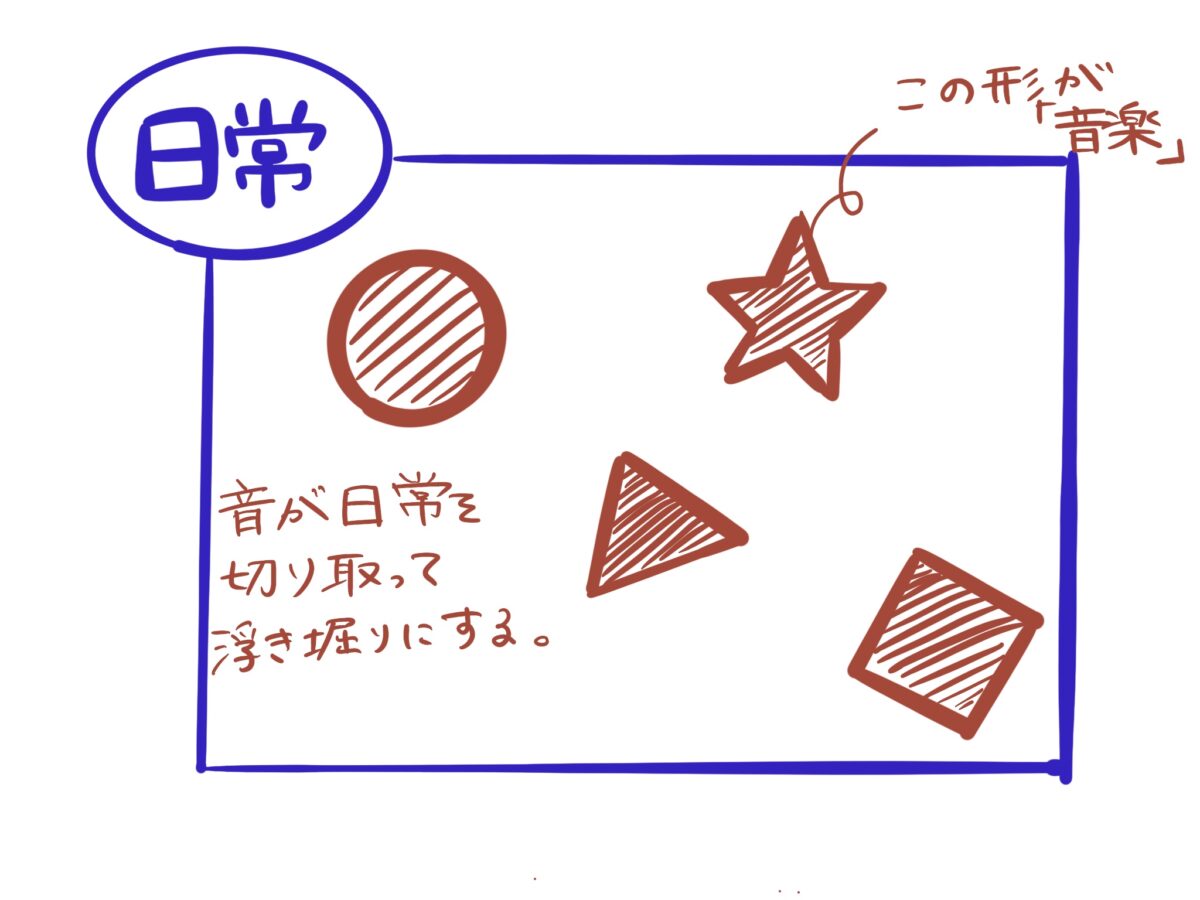
アレクサンドリア音楽隊と、ベイト・ハティクヴァの町が出会いが、その音楽を作り上げます。
はっきりと形になって見えてくるので、特別な何かを見たような気がする。
だけど、あくまでも普段見ている「日常」の域を出ない。そこから飛び出したものではないのです。本当はいつもそこにあって、本質は変わらない。変わらない景色だけど、普段見えない形になって見えてきます。
だから「何もなかった」ようで、ものすごく「何かあった」ようにも感じる。大きな事件がなくても、描かれた心の交流そのものに…ものすごく深い何かが。
だからこそ、ラストシーンは出会いと別れの「さみしさ」と「温かさ」。それぞれの人生が続いていくことに対して少しだけ灯った「希望」と、元の日常に戻る「諦め」全てを感じることが出来ます。
出会いはまるで小石の波紋のようで。広がって大きくなっていくかもしれないし、ひと広がりしたら、何事もなかったかのように、また静かな水面に戻ってしまうかもしれない。その希望と虚無の間を見た気がします。
あえてどこの感情にも振り切らせない、絶妙なバランス感覚さえ感じました。
彼らの人生も、観た私たちでさえも、どこか変わったような…。どこも変わらなかったような…。
それでも、文化や言葉を超えて「音楽」や「映画」、「恋」や「家族」を語らうことで、町の人たちと音楽隊は、お互いの人生をほんの少し交換したように見えました。
それは「うわべだけ平和」なお互いの国の人間が交換し合うには、あまりにも人間にとって本質的で、深い内容だったと思います。どこでどんな風に生きていても、悩みの本質は同じなのかも。
物語を通して、皆がものすごく親密になったわけではないし、トゥフィークとディナはロマンスにはならなかった。
パンフレットにあるように、「ハッピーエンド」も「バットエンド」も訪れないのです。
始まりそうではじまらない。何か起こりそうでおこらない。だけど生きていく中で、いつか思い出すであろう一日。
語られたそれぞれの人生の中に、教訓や意図はあると思います。誰もが失敗や後悔を経験して生きているので。
それでも作品全体として、何か大きなメッセージを強く伝えてこないのです。観ている側は、何を拾い上げたらいいのかも不確定で。決して誇張しないやり方が、美しく切なくもあり、残酷でもありました。
観劇の後に劇場を出て、「温かさ」にも「虚しさ」にも振りきれない感覚に戸惑いましたが、目の前の景色の中に見落としているもの、形になって届いていないものが沢山あるんだろうな…と思いました。
友だち、家族、街ゆく人。
目の前を生きている人が、どんな想いでそこに居るのか…。誰かの人生に、そっと耳を傾けたくなるような、そんな舞台でした。











2023年1月12日(日)
ホリプロ【ミュージカル バンズヴィジット ~迷子の音楽隊~】 @日生劇場 マチネ